第8回国際バイオロギングシンポジウム:環境配慮・次世代育成を意識した会議運営
2024年3月4日~8日、東京大学伊藤国際学術研究センターにて、「第8回国際バイオロギングシンポジウム(BLS8、The 8th International Bio-Logging Science Symposium)」が開催されました。3月4日~8日の本会議に合わせて、3月9日には高校生・大学生等一般向けの講演が開催されました。
本会議は動物に記録計を取り付けて生理・行動・生態・環境情報の取得を行うバイオロギング技術に関する世界最大の国際会議です。「バイオロギング(Bio-Logging )」は、バイオ(生き物)+ロギング(記録をとる)を組み合わせた新しい学術用語で、2003年に東京で第1回国際バイオロギングシンポジウムが開催された際に日本の研究者によって提案されました。今回、日本での開催は第1回以来2度目で、21年ぶりの開催となりました。
バイオロギングによる科学研究の世界的な発展に寄与するとともに、国内外のコミュニティーにとってバイオロギングの最新動向についての知見を得、また最先端の研究者と交流し自らの研究を発信する機会となりました。


サステナビリティに関する取り組み
3月4日から8日にかけて開催されたシンポジウムには、世界32か国から約400名の参加者が対面参加しました。
従来、シンポジウムの開催に際しては講演要旨を印刷した分厚い冊子が配布されることが通例でしたが、本シンポジウムではごく簡素化した数ページのフライヤーのみを配付し、全ての情報を会議のHP上に掲示することによって、紙の使用量を大きく削減することに成功しました。また水筒を配布し、ウォーターサーバーを会場内8箇所に配置した上で、コーヒーブレイク等での水筒の繰り返しの使用を呼びかけて、紙コップ等の消費やペットボトル飲料等の利用を削減しました。これらのサステナビリティの取り組みは会議HPでも公開を行い、参加者からの理解を得るようにしました。
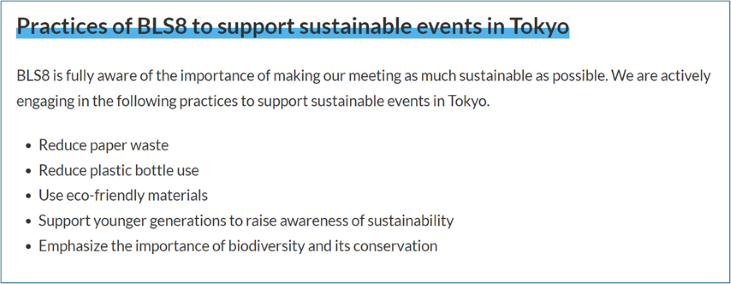

多くの参加者が配布したエコバックに水筒を入れて持ち運び、繰り返し休憩時に利用していました。参加者からも、「紙コップやプラスチックゴミ削減となってとても良い取り組みだと思う、エコバックやステンレスボトルは帰国してからも使い続けたい」といった声を聞き、好評でした。
また、幹事会では、野生動物の保護や生態系の保全に深く関わる学会として、今後も紙・プラスチックゴミ等の削減やカーボン・フットプリントに配慮した学会活動を行う方針が確認されました。
高校生・大学生等に向けた講演会開催
国際会議の開催に合わせて、3月9日に実施した高校生・大学生等に向けた講演会には、122名が対面参加し、90名がオンラインで講演を聴講しました。4件の講演の内、3件はNASAの宇宙飛行士をはじめとする外国人講師による英語の講演で、学生たちから多くの質問が出て活発な議論がなされました。特に次世代を担う我が国の若手研究者が世界の動向に直接触れ交流する機会として、有意義な場となりました。


開催時に活用された東京観光財団の各種支援
開催時は、東京観光財団の「環境配慮型MICE開催資金助成制度」によって、環境配慮に関する取り組みの一部や、高校生・大学生等地域住民に向けた講演会の一部支援を行いました。また、「国際会議開催支援プログラム」も提供し、無料の都内半日観光ツアーやホスピタリティチームの案内によって参加者が東京を楽しめたとのことで、開催時における当財団の支援を評価していただきました。
東京観光財団では、今後もMICEのサステナビリティに対する先進的な取り組み事例を積極的に発信していきます。

